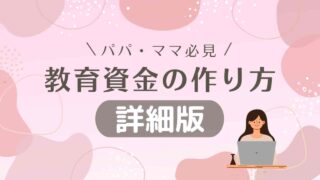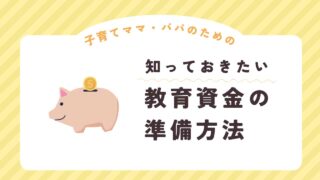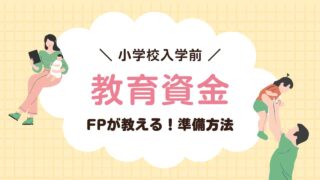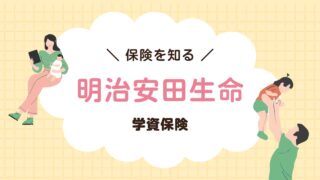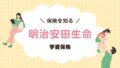学資保険に加入する際、多くの人は返戻率を重視して商品を選ぶが、実際の手取り額を左右するのは受取方法と税金の扱いである。一括受取は一時所得、分割受取は雑所得として課税され、確定申告の要否も異なってくる。
この記事では、受取方法による税金計算の違いや、一時所得と雑所得の確定申告のポイントを詳しく解説する。適切な受取方法の選択で、子どもの教育資金を最大限に活用する方法を学んでいこう。
学資保険の受取方法と税金の基本
学資保険は子どもの教育資金を準備するための保険商品だが、受け取る際に思っていたより金額が少なくなることがある。それは税金の影響である。受取方法によって適用される税金の種類が異なり、結果として手取り額に差が出てくるのだ。

専門家のワンポイントアドバイス:
この記事では、税金を考慮した場合の返戻率を確認します。パンフやランキングサイトの返戻率にとらわれず、家庭に合った保険選びには欠かせない考え方です。
一括受取と分割受取の税法上の扱い
学資保険には、大きく分けて二つの受取方法がある。一つは大学入学前に一括で受け取る方法、もう一つは在学中に分割で受け取る方法(小中学校入学時に受け取るタイプも含む)である。この受取方法の違いにより、適用される税金の種類が変わってくる。
一括受取の場合は「一時所得」として課税される。一時所得は、その年の収入から必要経費と特別控除額(50万円)を差し引いた金額の2分の1に課税される。
一方、在学中に分割で受け取る年金タイプの場合は「雑所得」として課税される。雑所得は、収入から必要経費を差し引いた全額が課税対象となる。
受取方法による税金の違い
受取方法によって税金の計算方法が異なるため、手取り額にも違いが出てくる。一括受取の場合、50万円を超えると所得税が発生するが、学資保険の返戻率から考えて、超える可能性は低い。
一方、分割受取の場合は毎年一定額の雑所得として扱われる。保険料は必要経費として差し引かれ、残った金額は給与所得などに合算される。基本的に受取額のほうが多くなるため、所得税率分、所得税がかかる。
このように、学資保険の受取額は税金の影響を受けて変動する。実際の手取り額を正確に把握するためには、自身の所得状況や家族構成などを考慮したうえで、税金の計算を行う必要がある。
なお、重要な点として、多くの学資保険では受取額から必要経費(支払保険料)を差し引いた利益部分が50万円以内に収まるケースが一般的である。この場合、一時所得の特別控除(50万円)により課税対象とならないことが多い。ただし、高額な学資保険や長期の運用で利益が大きくなる場合は、受取方法や受取人の選択により税負担を最適化することを検討すべきだ。
一時所得と雑所得:受取方法による税額計算の違い
学資保険の受取方法によって税金の影響が異なることは理解したが、実際にどの程度の違いが生じるのだろうか。ここでは、具体的な数字を用いて、一括受取と分割受取の場合の手取り額の違いを見ていく。比較のために、二つの学資保険のケースを考える。
一括受取の場合は、大学入学前に250万円受け取れる学資保険で、返戻率は106%、保険料は235.8万円である。分割受取の場合は、大学入学前に100万円、2年から4年で各50万円ずつ受け取れる学資保険で、返戻率は108%、保険料は231.5万円である。
これらのケースについて、所得税率が10%の場合と20%の場合で比較してみよう。
一時所得の計算方法と確定申告
一括受取の場合、受取額250万円から保険料235.8万円を差し引いた14.2万円が一時所得となる。特別控除50万円を適用すると、課税所得は0円となり、所得税は発生しない。手取り額は250万円で、返戻率は変わらず106%である。
一方、分割受取の場合、初年度の100万円は一時所得として扱われる。必要経費として差し引く保険慮は按分する。
大学入学前に受け取る100万円について、必要経費は92.6万円(231.5万円×100万円/250万円)となり、7.4万円が一時所得となる。特別控除50万円を適用すると、課税所得は0円となり、所得税は発生しない。
2年目以降は、各年50万円から46.3万円(231.5万円×50万円/250万円)を差し引いた3.7万円が雑所得となる。10%の税率を適用すると、各年の所得税は0.37万円(合計額1.11万円)となる。4年間の合計で、手取り額は約248.89万円となり、返戻率は約107.5%に下がる。
【一時所得の場合の確定申告について】
一時所得として扱われる一括受取の場合、確定申告が必要となるのは、一時所得の金額(特別控除50万円適用後)が大きい場合である。具体的な手順は以下の通りだ。
- 確定申告の要否の判断
一時所得の金額が20万円以下の場合:原則として確定申告不要
一時所得の金額が20万円を超える場合:確定申告が必要 - 必要書類
確定申告書B
学資保険の満期金支払通知書(保険会社から送付)
保険料の支払い証明書または契約内容確認書 - 申告の期限
受け取った翌年の2月16日~3月15日までに申告
なお、給与所得者で一時所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告を行わなくても年末調整で処理できる。所得税の確定申告を行った場合は、その情報が市区町村に通知されるため、住民税のための別途申告は不要である。
雑所得の計算方法と確定申告
一括受取の場合、所得税率が変わっても課税所得が0円であることに変わりはないため、手取り額は250万円のままである。
分割受取の場合、初年度の一時所得に対する税金は発生しない。2年目以降の雑所得に20%の税率が適用される。各年約0.74万円の所得税が発生する。4年間の合計で、手取り額は約247.78万円となり、返戻率はさらに約107%に下がる。
| 返戻率の変化 | 一括受取のみ | 一括受取+年金形式 |
|---|---|---|
| 表面上の返戻率 | 106% | 108% |
| 所得税率10% | 106% | 107.5% |
| 所得税率20% | 106% | 107% |
このように、所得税率や受取方法によって手取り額に違いが生じることがわかる。今回のケースでは、分割受け取りにより、所得税率20%の場合では、約1%下がることがわかった。実際の選択にあたっては、家計の状況や教育費の必要時期なども考慮する必要があるため、税金だけでは判断できないが、手取額も考えておきたい。
分割受取で雑所得として扱われる場合、毎年の受取時に確定申告の検討が必要となる。雑所得の確定申告には以下のポイントがある。
- 雑所得の申告基準
給与所得者で雑所得を含む給与所得以外の所得が20万円以下:確定申告不要
給与所得者で雑所得を含む給与所得以外の所得が20万円超:確定申告必要
給与所得がない場合:雑所得が基礎控除(48万円)を超えると確定申告必要 - 雑所得の申告方法
確定申告書B「雑所得」欄に記入
「雑所得の内訳書」の添付が必要
収入金額から必要経費(按分した保険料)を差し引いた金額を記入 - 複数年にわたる注意点
分割受取の場合、複数年にわたって毎年確定申告の検討が必要
保険料の按分計算は毎年同じ方法で行う必要がある
前年の申告内容を参考にして一貫性を保つことが重要

専門家のワンポイントアドバイス:
返戻率の高さを優先し、受取時期を考慮しない場合、必要な時期に必要な資金を受け取れない一方、想定ほどの金額を受け取れない可能性があります。
確定申告のポイント:受取方法別の注意点
学資保険の受取方法によって税金の影響が異なることが分かったが、では実際にどのように受取方法を選べば良いのだろうか。ここでは、一括受取と分割受取それぞれのメリット・デメリットを整理し、家計状況に応じた最適な選び方を解説する。

専門家のワンポイントアドバイス:
税金を考慮した返戻率について解説しましたが、税金だけ考慮すればいいわけではありません。しかし、返戻率が高ければとりあえず良い、と考えないように注意した方がいいでしょう。
一括受取と分割受取のメリット・デメリット
一括受取のメリットは、税金の影響を受けにくく、大きな金額を一度に受け取れることだ。特に大学入学時の多額の費用に対応しやすいのが大きな利点である。一方で、デメリットとしては、受け取った後の資金管理が必要となることが挙げられる。
分割受取のメリットは、教育費用の支払いに合わせて定期的に資金を受け取れることだ。これにより、長期的な資金計画が立てやすくなる。デメリットとしては、毎年の所得に上乗せされるため、税金の影響を受けやすいことが挙げられる。
家計の所得状況別:税金面で有利な受取方法
最適な受取方法を選ぶためには、以下の点を考慮する必要がある。
- 教育費用の支払いタイミング:大学入学時に多額の費用が必要な場合は一括受取、在学中に継続的に費用が発生する場合は分割受取が適している可能性が高い。
- 家計の収入状況:所得が高く、高い税率が適用される場合は、一括受取のほうが税金の影響を抑えられる可能性がある。
- 資金管理能力:一括で大きな金額を受け取った際に、適切に管理し運用できる自信がある場合は一括受取が有利かもしれない。
- 将来の金利動向:分割受取の場合、将来の金利上昇によって運用益が増える可能性がある。一方、金利が低下する場合は一括受取のほうが有利になる可能性がある。
最適な受取方法は各家庭の状況によって異なるため、自身の状況を客観的に分析し、必要に応じてファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめする。
このように、学資保険の受取方法を選ぶ際には、税金の影響だけでなく、家計の状況や将来の見通しなども総合的に判断することが重要である。次のセクションでは、これらの点を踏まえた上で、学資保険の受取額を最大化するための心得をまとめる。

専門家のワンポイントアドバイス:
一時所得と雑所得の区別は、商品ごとに調べる必要があります。名称だけでは判断できません。たとえば、
・日本生命 こども祝金:一時所得、学資年金:雑所得
・明治安田生命 教育資金・満期保険金ともに雑所得
・アフラック生命 学資一時金:一時所得、学資年金:雑所得
のように、パンフレットやウェブサイトで確認すると、課税関係が保険会社によって異なります。
保険選びの基本ですが、ネットの情報をうのみにせず、直接問い合わせて確認することが大切です。
まとめ:受取方法と税金を考慮した学資保険選びのポイント
学資保険の受取方法によって適用される税金の種類や計算方法が異なることを見てきた。一括受取は一時所得として、分割受取は雑所得として扱われ、それぞれ税金の計算方法や確定申告の要否が変わってくる。
教育資金を最大限に活用するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要である。
- 税金の種類を理解する: 一括受取の一時所得には50万円の特別控除があり、分割受取の雑所得にはそのような控除がない点を理解する。
- 自身の所得状況を考慮する: 所得税率や他の所得の状況によって、どちらの受取方法が有利かが変わる可能性がある。
- 教育資金の必要時期を見極める: 税金面だけでなく、実際に教育費が必要となるタイミングに合わせた受取方法を選択する。
- 確定申告の要否を事前に確認する: 特に分割受取の場合は、毎年の確定申告について理解しておく。
- 保険商品選びの段階で検討する: 契約前に受取方法のオプションや税金の取扱いについて保険会社に確認しておく。
学資保険は子どもの未来のための大切な資金準備手段である。税金の影響を理解し、適切な受取方法を選択することで、より効果的に教育資金を確保することができる。最後に、学資保険だけでなく、他の資産形成手段も併せて検討し、総合的な教育資金計画を立てることをおすすめする。
受取方法による税金の影響は個人の状況によって大きく異なるため、必要に応じてファイナンシャルプランナーや税理士などの専門家に相談することも検討すべきである。適切な選択により、子どもの大切な教育資金を効率的に準備し、活用することができるだろう。
- Q学資保険の一括受取と分割受取では、どちらが税制上有利ですか?
- A
一概には言えません。一括受取は一時所得として扱われ、特別控除(50万円)が適用されるため、多くの場合は税金の影響が小さくなります。一方、分割受取は雑所得として毎年課税されますが、他の所得と合算されるため、総合的な税負担を考慮する必要があります。個々の状況に応じて判断することが重要です。
- Q学資保険の受取時に確定申告は必要ですか?
- A
一括受取の場合、一時所得が50万円を超える場合に確定申告が必要です。分割受取の場合、給与所得がある方は年末調整で処理されることが多いですが、他の所得と合わせて20万円を超える場合は確定申告が必要となります。詳細は税務署やファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
- Q学資保険以外の教育資金準備方法はありますか?
- A
はい、あります。例えば、株式や投資信託などの金融商品を活用した資産運用、教育ローン、ジュニアNISAなどが挙げられます。それぞれメリット・デメリットがあるため、家計の状況や教育プランに合わせて選択することが大切です。複数の方法を組み合わせることも効果的な戦略の一つです。