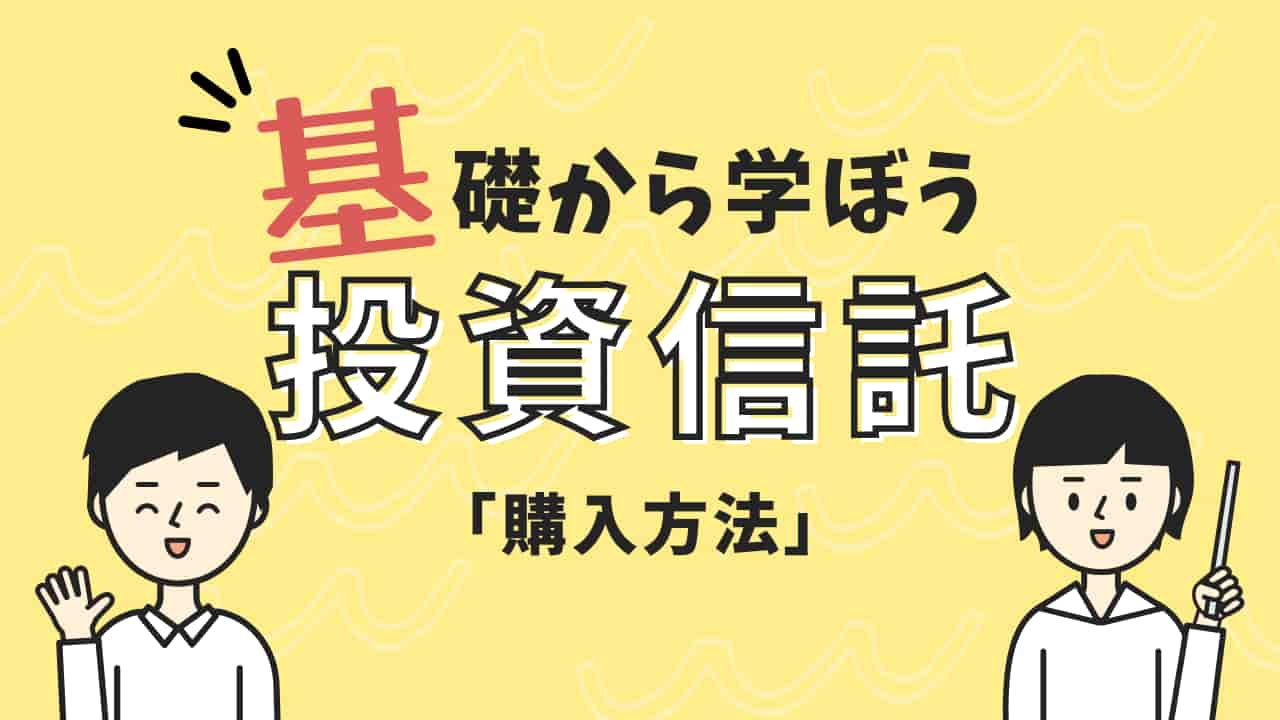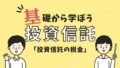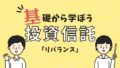投資信託を購入する方法は、銀行窓口、証券会社、ネット証券など、複数の選択肢がある。最新のデータによると、74.5%の投資家がネット証券を利用している一方で、対面での相談を重視する投資家も依然として多い。
この記事では、投資信託の購入・売却方法と約定の仕組みについて解説する。初めて投資信託を売買する方も、取引のタイミングや資金の動きを正確に把握できるよう、実践的な情報を提供する。長期的な資産形成を成功させるための基本的な知識を身につけよう。
投資信託の売買の基本
投資信託の売買には、購入時と売却時それぞれで押さえるべきポイントがある。投資信託は株式とは異なり、注文から約定、受渡までの流れが独特であり、この仕組みを理解しておくことが取引をスムーズに行うための基本となる。
購入方法については多様な選択肢があり、銀行窓口、証券会社、ネット証券などの特徴を理解して自分に合った方法を選ぶことが重要である。また売却時には、税金や手数料の計算方法、資金化までの日数などを把握しておく必要がある。
投資信託の取引では、注文日・約定日・受渡日という3つの日付が重要な意味を持つ。これらの日付と価格決定のタイミングを理解することが、効果的な売買を行うための第一歩である。
約定日・受渡日の仕組み
投資信託の取引では、注文日・約定日・受渡日という3つの日付が重要な意味を持つ。これらの日付の関係を理解することで、資金の動きを正確に把握できる。
約定日とは、投資信託の購入や売却が成立する日のことであり、基準価額が確定する日である。投資信託は、株式などとは異なり、注文した時点の価格ではなく、約定日の基準価額で取引が成立する。
受渡日とは、実際にお金の受け渡しが行われる日のことである。購入の場合は口座から資金が引き落とされる日、売却の場合は口座に資金が入金される日となる。
投資信託の種類や金融機関によって、注文日から約定日、受渡日までの日数は異なる。一般的には以下のようなパターンとなる:
- 国内投資信託の場合
- 購入:注文日の翌営業日が約定日、約定日の翌営業日が受渡日
- 売却:注文日の翌営業日が約定日、約定日から起算して原則4営業日目が受渡日
- 外国投資信託の場合
- 購入・売却ともに、注文日から約定日までが2〜3営業日、約定日から受渡日までが3〜5営業日かかることが多い
このような日数の差は、投資対象の市場が国内か海外かによって異なり、海外市場の場合は現地の休日やタイムラグなどの影響を受ける。
また、ファンドによっては特定の日のみ取引可能な場合や、大量の解約があった場合に一時的に解約を制限する場合もあるため、各ファンドの目論見書や販売会社の規定を確認しておくことが重要である。
投資信託の購入方法
投資信託を購入する際には、銀行や証券会社の窓口で対面による購入とネット経由での購入という2つの主な方法がある。それぞれの方法には特徴やメリット・デメリットがあるため、自分の投資スタイルや目的に合った方法を選ぶことが重要となる。ここでは、それぞれの購入方法の流れと詳細を解説する。
銀行・証券会社などの窓口(対面)での購入
投資信託を対面で購入する場合の、一般的な手順を紹介する。手順を理解し、スムーズな手続きを実現したい。
- STEP1購入したい投資信託を選択
- 自分の投資目的やリスク許容度に合った投資信託を選択する。
- 投資信託の目論見書や運用報告書を読み、商品の特徴や過去の運用実績を確認する。
- 自分の投資目的(資産形成、退職後の資金確保など)に合った商品を選ぶ。
- リスク許容度(元本割れのリスクをどの程度許容できるか)を考慮して、商品を選択する。
- 複数の投資信託を比較検討し、最終的に購入する商品を決定する。
- 自分の投資目的やリスク許容度に合った投資信託を選択する。
- STEP2銀行や証券会社の窓口に行き、担当者に投資信託の購入を申し出る
- 選択した投資信託を購入したい旨を担当者に伝える。
- 担当者から、購入手続きの流れについて説明を受ける。
- STEP3担当者から投資信託の説明を受け、質問があれば尋ねる
- 担当者から、選択した投資信託の特徴や仕組み、リスクについて詳しい説明を受ける。
- 投資信託の運用方針、投資対象、手数料などについて説明を受ける。
- 分配金の仕組みや税金についても確認する。
- 理解できない点があれば、遠慮なく質問する。
- 担当者から、選択した投資信託の特徴や仕組み、リスクについて詳しい説明を受ける。
- STEP4口座開設に必要な書類を記入し、本人確認書類を提示する
- 投資信託購入のために、口座開設が必要な場合は、申込書に必要事項を記入する。
- 申込書に必要事項を記入し、届出印を押印する。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を提示する。
- すでに口座を開設している場合は、必要に応じて書類の更新や確認を行う。
- 投資信託購入のために、口座開設が必要な場合は、申込書に必要事項を記入する。
- STEP5購入する投資信託の金額を指定し、注文を行う
- 購入する投資信託の金額を指定する。
- 注文書に必要事項を記入し、署名や捺印を行う。
- 注文が受理されたことを確認する。
- STEP6代金を支払い、取引が完了
- 指定した購入金額を支払う。
- 現金で支払う場合は、窓口で現金を手渡す。
- 口座振替で支払う場合は、指定した口座から購入金額が引き落とされる。
- 購入した投資信託が口座に反映されたことを確認する。
- 取引報告書や残高報告書を受け取り、内容を確認する。
- 指定した購入金額を支払う。
以上が、銀行や証券会社の窓口で投資信託を購入する際の一般的な流れと詳細である。金融機関によって多少の違いがある場合があるため、必ず事前に確認することをすすめる。
銀行・証券会社などのネット経由での購入
投資信託をネットで購入する場合の、一般的な手順を紹介する。ネットの場合、基本的に自分で必要書類を集め、確認しなければならないため、手順を理解し、スムーズな手続きを実現したい。
- STEP1購入したい投資信託を選択
- ネット上で提供されている投資信託の情報を確認し、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選択する。
- 各金融機関のウェブサイトで、投資信託の一覧や詳細情報を確認する。
- 投資信託の目論見書や運用報告書をダウンロードし、商品の特徴や過去の運用実績を確認する。
- 自分の投資目的(資産形成、退職後の資金確保など)に合った商品を選ぶ。
- リスク許容度(元本割れのリスクをどの程度許容できるか)を考慮して、商品を選択する。
- 複数の投資信託を比較検討し、最終的に購入する商品を決定する。
- ネット上で提供されている投資信託の情報を確認し、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選択する。
- STEP2銀行や証券会社のウェブサイトにアクセスし、口座開設を申し込む
- 選択した金融機関のウェブサイトにアクセスし、口座開設のページを探す。
- 必要事項を入力し、口座開設を申し込む。
- 氏名、住所、連絡先、職業など、必要な個人情報を入力する。
- 口座の種類(特定口座、NISA口座など)を選択する。
- 暗証番号や取引パスワードを設定する。
- STEP3口座開設に必要な情報を入力し、本人確認書類をアップロードする
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の画像をアップロードする。
- マイナンバーの提供が必要な場合は、マイナンバーカードの画像や通知カードとの本人確認書類の画像をアップロードする。
- 金融機関から届いた書類に署名や捺印を行い、それらの画像をアップロードする。
- STEP4ネット上で投資信託の説明を読み、質問があれば電話やメールで問い合わせる
- 選択した投資信託の詳細情報を確認する。
- 投資信託の運用方針、投資対象、手数料などについて説明を読む。
- 分配金の仕組みや税金についても確認する。
- 理解できない点があれば、電話やメールで問い合わせる。
- 多くの金融機関では、専用の問い合わせフォームやチャットサービスを提供している。
- 電話での問い合わせも可能な場合が多い。
- 選択した投資信託の詳細情報を確認する。
- STEP5購入する投資信託の金額を指定し、注文を行う
- ログインして、投資信託購入のページを開く。
- 購入する投資信託の金額を指定する。
- 注文内容を確認し、確定する。 注文が受理されたことを確認する。
- STEP6代金を振り込み、取引が完了
- 指定した購入金額を振り込む。
- インターネットバンキングやATMを利用して、指定の口座に購入金額を振り込む。
- 振込手数料がかかる場合があるので、事前に確認する。
- 購入した投資信託が口座に反映されたことを確認する。
- 取引報告書や残高報告書をダウンロードし、内容を確認する。
- 指定した購入金額を振り込む。
以上が、銀行や証券会社のネット経由で投資信託を購入する際の一般的な流れと詳細である。金融機関によって多少の違いがある場合があるため、必ず事前に確認しよう。
投資信託の売却プロセスを詳しく解説
投資信託の売却は購入と同様に重要なプロセスであり、適切な手順とタイミングを理解しておくことが必要である。ここでは、投資信託の売却プロセスについて詳しく解説する。
売却注文の出し方と種類
投資信託の売却注文には、「金額指定」と「口数指定」の2種類の方法がある。それぞれの特徴と具体的な手順を理解し、自分に合った売却方法を選択することが重要である。
金額指定売却は、売却したい金額を指定する方法である。例えば、50万円分の解約を指定すると、約定日の基準価額をもとに自動的に売却口数が計算される。この方法は、必要な金額を正確に換金したい場合に適している。ただし、実際に受け取れる金額は約定日の基準価額によって変動するため、指定した金額と完全に一致するわけではない。
口数指定売却は、保有している投資信託の口数をもとに売却数量を指定する方法である。例えば、保有口数の半分を売却するといった指定ができる。この方法は、保有比率を調整したい場合や、一部売却して様子を見たい場合に適している。受取金額は約定日の基準価額×売却口数で計算されるため、売却時点では正確な金額がわからない。
売却注文の具体的な手順は、購入時と同様に対面チャネルとネットチャネルの2つの方法がある。以下にそれぞれの流れを示す。
窓口(対面)での売却手順
- 金融機関の窓口に行き、担当者に投資信託の売却を申し出る
- 必要書類(本人確認書類など)を提示する
- 売却方法(金額指定または口数指定)を選択する
- 売却申込書に必要事項を記入し、届出印を押印する
- 担当者から受付確認を受ける
- 受渡日に指定した口座に売却代金が入金される
ネット経由での売却手順
- 金融機関のウェブサイトにログインする
- 投資信託の売却(解約)メニューを選択する
- 売却したい投資信託を選択する
- 売却方法(金額指定または口数指定)を選択し、金額または口数を入力する
- 売却内容を確認し、注文を確定する
- 受渡日に指定した口座に売却代金が入金される
売却注文は原則として営業時間内であれば当日中のキャンセルが可能だが、翌営業日以降のキャンセルはできない。また、一度売却注文が約定すると取り消しができないため、注文時には内容をよく確認することが重要である。
売却時の手数料と税金
投資信託を売却する際には、手数料と税金についての知識が不可欠である。これらを事前に理解しておくことで、売却後に受け取れる実際の金額を正確に計算できる。
売却時に発生する可能性のある主な手数料は信託財産留保額である。これは投資信託の解約時に信託財産から差し引かれる費用で、残存受益者の利益を守るために設定されている。信託財産留保額は、基準価額に対して0%〜1%程度の料率で設定されており、ファンドによって異なる。インデックスファンドやETFには信託財産留保額がない場合が多い。
売却時の税金は、投資信託の売却益(譲渡益)に対して課税される。譲渡益は「売却価額 – 取得価額 – 売却に要した費用」で計算され、これに対して約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で課税される。損失が出た場合(譲渡損)は、同一年内の他の上場株式や投資信託の譲渡益と相殺することができる。
税金の計算において重要なのが「取得価額」である。複数回に分けて購入した場合は、平均取得単価または移動平均法による計算が一般的である。また、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、証券会社等が自動的に税金を計算して徴収してくれるため、確定申告が不要となる利点がある。
NISA(少額投資非課税制度)で購入した投資信託を売却した場合は、売却益が非課税となる。ただし、非課税期間内に売却することが条件であり、非課税期間が終了した後に売却した場合は通常通り課税される。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の場合は、運用中の売却には税金がかからないが、最終的な受取時に退職所得または公的年金等として課税される仕組みとなっている。
売却金の受け取りまでの流れ
投資信託を売却してから実際に資金を受け取るまでには、いくつかのステップと一定の日数がかかる。この流れを理解しておくことで、資金計画を適切に立てることができる。
売却注文から着金までの一般的な流れは以下の通りである:
- 売却注文日(T日):売却の申込みを行う日
- 約定日(T+1営業日):売却が成立し、基準価額が確定する日
- 受渡日(T+4〜7営業日):売却代金が指定した口座に入金される日
この日数は、投資信託の種類や金融機関によって異なる。国内投資信託の場合は一般的に約定日から3〜4営業日後、外国投資信託の場合は約定日から4〜7営業日後に受渡しとなる場合が多い。
特に急ぎの資金が必要な場合は、この日数を考慮して早めに売却注文を出す必要がある。例えば、週末を挟む場合や祝日がある場合は、さらに日数がかかることがある。また、海外の市場が休場の場合は、外国投資信託の売却手続きに遅れが生じる可能性もある。
一部の金融機関では、売却代金の即日入金サービスを提供している場合もあるが、これは通常、追加手数料がかかることが多い。また、大口の解約については、一度に売却せずに複数回に分けて売却することで、市場への影響を軽減する方法もある。
売却金の受け取り方法としては、証券会社や銀行の預かり金口座に入金される場合と、指定した銀行口座に自動的に振り込まれる場合がある。預かり金として受け取った場合は、再投資に回すか、出金するかを選択できる。
投資信託の購入場所の選び方
投資信託の購入場所によって、サービス内容や手数料が異なるため、自分に合った選択が重要である。購入場所には主に銀行、証券会社、ネット証券の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがある。
【データ】投資信託の購入経路
東証マネ部「お金に関するアンケート」によると、投資信託の購入経路として最も多かったのが、ネット証券の74.5%で、銀行の27.9%が次に続いた。信託銀行や郵便局、保険会社などの購入経路も一定の割合を占めており、投資家がそれぞれのニーズや投資スタイルに合わせて多様な購入経路を選択していることがわかる。
| 購入経路 | 割合 |
|---|---|
| オンライン証券(ネット証券) | 74.5% |
| 銀行 | 27.9% |
| 対面の証券会社 | 23.9% |
| 信託銀行 | 18.4% |
| 郵便局 | 15.3% |
| 保険会社 | 7.4% |
| 企業型DCで選択 | 5.8% |
| その他 | 0.3% |
銀行での購入のメリット・デメリット
銀行で投資信託を購入する最大のメリットは、対面での相談が可能な点である。特に投資初心者にとっては、担当者から丁寧な説明を受けられることが大きな安心につながる。また、普段から利用している銀行で購入できるため、新たに口座を開設する手間がかからない点も便利である。
一方でデメリットとしては、取扱商品が限られていることが挙げられる。銀行では自社グループの運用会社が提供する商品が中心となることが多く、選択肢が少ない傾向にある。また、銀行窓口での購入は手数料が比較的高いことも特徴である。購入時の販売手数料は最大3.3%程度かかることが一般的であり、長期投資の収益を圧迫する要因となりうる。
証券会社での購入のメリット・デメリット
証券会社での購入は、専門的なアドバイスを受けられる点が大きなメリットである。証券会社の営業担当者は投資の専門家であり、市場動向や商品知識について詳しい情報を提供してくれる。また、銀行よりも多様な商品ラインナップがあり、自分のニーズに合った商品を選びやすい。
デメリットとしては、銀行と同様に対面での購入となるため、手数料が比較的高いことが挙げられる。また、証券会社の営業時間内に店舗に足を運ぶ必要があるため、仕事で忙しい人にとっては時間的な制約が生じる。さらに、証券会社によってはセールス色が強く、必ずしも顧客の利益を最優先にした提案をしない場合もあるため、複数の証券会社を比較検討することが望ましい。
ネット証券での購入のメリット・デメリット
ネット証券の最大のメリットは、手数料の安さである。多くのネット証券では、購入時の販売手数料が無料の投資信託(ノーロード)を豊富に取り揃えている。また、24時間いつでも注文できる利便性と、多様な商品ラインナップも大きな魅力である。さらに、スマートフォンアプリでの取引が可能な点も、若年層を中心に支持されている理由の一つである。
一方のデメリットは、自己判断での商品選択が必要な点である。対面でのアドバイスがないため、投資初心者にとってはどの商品を選べばよいか迷うケースも少なくない。また、インターネットの操作に不慣れな人にとっては、取引画面の操作が難しく感じられることもある。システム障害時には取引ができなくなるリスクも考慮する必要がある。
このように、投資信託の購入場所にはそれぞれ特徴があり、自分の投資経験や知識レベル、重視するポイント(コスト、サポート、商品ラインナップなど)に応じて選択するのが賢明である。
投資信託の約定の仕組みと注意点
投資信託の取引では、株式や債券などの他の金融商品とは異なる独自の約定ルールが適用される。この仕組みを理解することで、効果的な売買戦略を立てることができる。
基準価額の決定タイミング
投資信託の取引価格となる基準価額は、一般的に1日1回、市場終了後に算出される。このタイミングを理解することが、投資信託の売買において重要なポイントとなる。
多くの投資信託では、基準価額は原則として毎営業日、その日の市場終了後に計算される。具体的には、日本の株式市場が閉まる午後3時以降に、その日の市場における投資対象の価格をもとに計算される。この計算された基準価額は、翌営業日の朝までに公表される。
重要なのは、投資家が注文を出すときには、その時点での基準価額はまだ確定していないということである。例えば、午前10時に購入注文を出した場合、その日の市場終了後に計算される基準価額で約定することになる。
外国株式や外国債券を投資対象とする投資信託の場合は、さらに複雑である。例えば、米国株式を主な投資対象とするファンドでは、日本時間の朝に注文を出しても、米国市場がまだ開いていないため、その日の米国市場終了後(日本時間では翌日の朝)に計算される基準価額で約定することになる。
ファンドによっては、注文の締切時間(カットオフタイム)が設定されている場合がある。このカットオフタイムまでに注文を出せば当日扱いとなり、それを過ぎると翌営業日扱いとなる。一般的なカットオフタイムは午後3時頃であることが多いが、ファンドによって異なるため、事前に確認が必要である。
購入時と売却時の約定日の違い
投資信託の取引では、購入時と売却時で約定日や受渡日が異なることがある。この違いを理解することで、資金計画を適切に立てることができる。
購入の場合、一般的に注文日の翌営業日が約定日となる。例えば、月曜日に注文を出した場合、火曜日が約定日となる。購入代金の支払いは、約定日と同日または翌営業日に行われることが多い。
売却の場合も、一般的に注文日の翌営業日が約定日となる。しかし、売却代金の受け取り(受渡日)は、約定日から数日後となることが多い。国内投資信託の場合は約定日から3〜4営業日後、外国投資信託の場合は4〜7営業日後が一般的である。
この違いは、投資信託の償還(解約)においては、投資対象となる資産の売却や資金回収に時間がかかるためである。特に外国投資信託の場合は、海外市場での取引や為替取引、資金移動に時間を要する。
また、購入時と売却時では基準価額の算出に含まれる手数料等も異なる場合がある。購入時には基準価額に販売手数料が上乗せされる場合があり、売却時には基準価額から信託財産留保額が差し引かれる場合がある。これらの手数料等は、投資信託の種類や販売会社によって異なるため、事前に確認が必要である。
取引のタイミングと注意点
投資信託の売買を行う際には、市場の変動と約定のタイミングに関するいくつかの注意点を理解しておくことが重要である。
投資信託の価格は、注文時点ではなく約定日の基準価額で決まるため、市場の急変動時には注意が必要である。例えば、株価が大きく下落している日に購入注文を出した場合、翌営業日にさらに下落していれば、予想よりも安い価格で購入できることになる。逆に、翌営業日に株価が反発していれば、予想よりも高い価格での購入となる。
このような特性から、投資信託の売買に「タイミング」を図ることは難しい。そのため、投資信託では長期・分散・積立といった投資手法が推奨されることが多い。特に定期的に一定額を購入する「ドルコスト平均法」は、価格変動のリスクを平準化する効果がある。
市場の急変動時には、大量の解約(売却)注文が集中することがある。このような場合、ファンドによっては一時的に解約を制限する「解約制限」や「解約停止」が実施されることがある。これは、残存する投資家の利益を保護するための措置であり、ファンドの規約で定められている。
また、投資信託の中には、特定の日にしか取引できない「クローズド期間」を設けているものもある。これは、運用の安定性を確保するためのものであり、特に不動産やプライベートエクイティなどの流動性の低い資産を投資対象とするファンドに多い。
取引の注文方法についても注意が必要である。株式のような「指値注文」や「成行注文」の概念はなく、基本的には「成行注文」のみとなる。また、「逆指値注文」(ストップロス注文)のような自動売却の仕組みもないため、価格変動を自分でモニタリングする必要がある。
これらの特性を理解した上で、自分の投資目的や資金計画に合った取引を行うことが重要である。短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、長期的な視点で運用することが、投資信託を活用する上での基本的な姿勢である。
まとめ:スムーズな投資信託の売買のポイント
投資信託の売買をスムーズに行うには、約定の仕組みを理解し、適切な購入場所の選択と売却プロセスの知識が重要である。購入方法は銀行、証券会社、ネット証券など複数の選択肢があり、それぞれの特徴を理解して自分に合った方法を選ぶことが大切である。
売却に関しては、金額指定と口数指定の違いを理解し、売却タイミングを適切に判断することが必要である。また、売却時の手数料や税金についても事前に把握しておくことで、予想外の出費を避けることができる。
投資信託の約定の仕組みは、注文日と約定日の関係、基準価額の決定タイミング、受渡日までの日数など、株式などの他の金融商品とは異なる特徴がある。これらの特性を理解した上で、自分の資金計画に合わせた取引を行うことが重要である。
特に急ぎの資金が必要な場合は、売却から着金までの日数を考慮して早めに手続きを行うことが必要である。また、市場の急変動時には冷静な判断が求められ、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、長期的な視点での運用を心がけることが大切である。
投資信託は長期運用に適した金融商品であり、売買のタイミングを過度に意識するよりも、定期的な積立やリバランスといった手法を活用することで、時間の力を味方につけた効果的な資産形成が可能となる。
- Q投資信託の売却時、金額指定と口数指定はどちらがおすすめですか?
- A
必要な目的によって使い分けるのがおすすめです。急な出費に対応するなど明確な金額が必要な場合は金額指定、ポートフォリオのリバランスなど保有比率の調整が目的なら口数指定が適しています。金額指定では約定日の基準価額で実際の売却金額が変動する点に注意が必要です。
- Q投資信託の売却から着金までは実際何日かかりますか?
- A
国内投資信託の場合、一般的には売却注文日から4〜5営業日で着金します。具体的には、注文日の翌営業日が約定日となり、約定日から3〜4営業日後に資金が指定口座に入金されます。外国投資信託ではさらに日数がかかり、注文日から最大7営業日程度必要な場合もあります。
- Q投資信託の約定価格はいつ決まるのですか?
- A
投資信託の約定価格(基準価額)は、注文日の翌営業日に決まります。注文日の市場終了後(通常は15時以降)に基準価額が計算され、翌営業日朝に確定します。このため、注文時点では取引価格が確定していない「未知の価格」での注文となります。海外資産を含むファンドでは、さらに複雑なタイムラグが生じます。