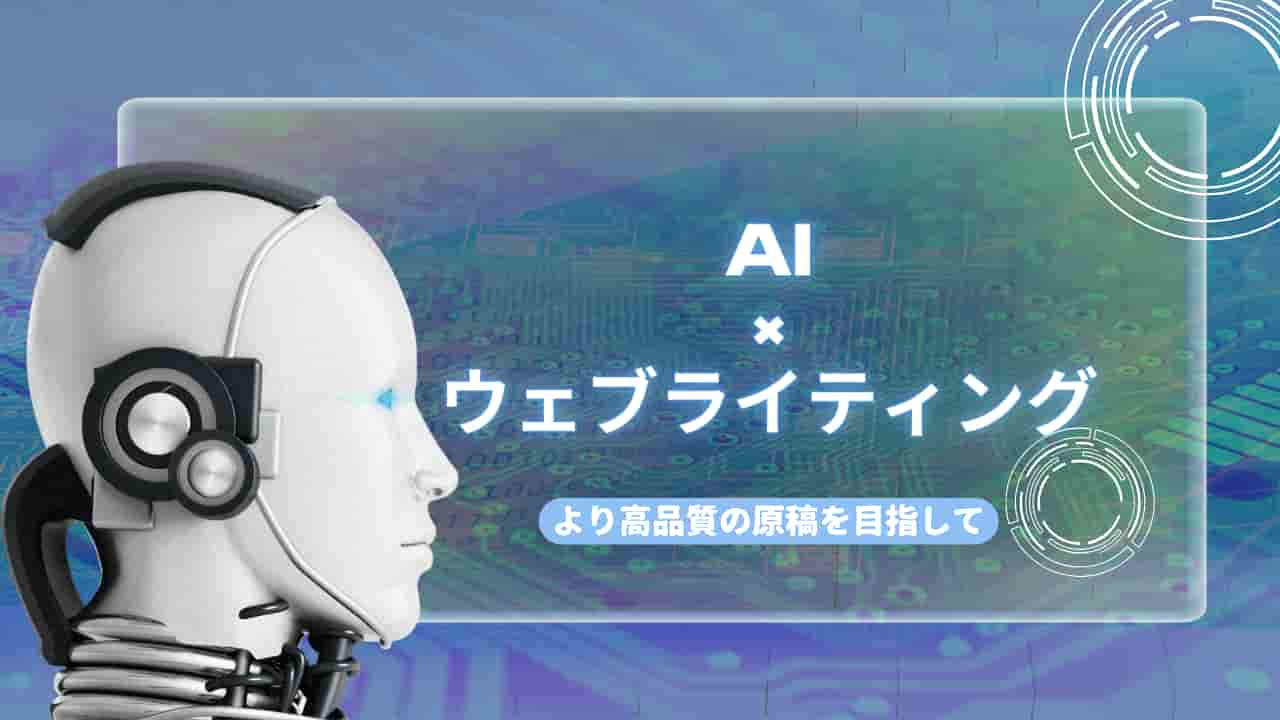文章生成AIであるChatGPTやCopilotを使って「相続時精算課税制度」について質問し、得られた回答を分析することで、AIの適切な使用方法や課題について考察した。
その結果、AIによって生成された文章をそのまま使用するのではなく、情報の正確性の確認や専門家による校閲の必要がある。
オリジナリティのある質の高いコンテンツを作成するためには、AIによって生成された文章を編集し、独自の見解や情報を追加することが求められる。
ChatGTPが浸透してから、案件のごく一部だが、ChatGTPやCopilotの使用を認めるものもある。しかし、ほとんどが使用禁止で、クライアントも一度は、AIの性能を試したものと思われる。アイデア出しなどには使えるChatGTPやCopilotでも、マネー分野で説得力のある記事を書かせるのは難しいのが現状だ。
しかし、AIの技術は日々進歩している。近い将来、思い通りの原稿を書く可能性もある。そこで、AIにどのような指示をすれば期待通りの文章ができるか試みる。
ChatGTP3.5に「相続時精算課税制度」について質問する
まず「相続時精算課税制度」について、条件や情報を与えず、「相続時精算課税制度について教えて」と質問した。
相続時精算課税制度は、日本の相続税法において用いられる制度の一つです。この制度では、相続人が相続財産を相続した際に、相続税の支払いを繰り延べる代わりに、その財産について毎年一定の金額を所得として申告し、所得税を支払うこととなります。
具体的には、相続財産の評価額から相続税を差し引いた金額が、相続人が実際に手に入れた相続財産の取得価格となります。そして、この取得価格から毎年一定の金額を差し引いた額が、その年の所得として課税されます。
この制度により、相続財産の価値が現金化されるまでにかかる期間や、その際の負担を軽減することができます。また、資産の評価や支払い方法によって、税金の支払いに関する柔軟性も増すことができます。
ただし、相続時精算課税制度は、所得税の支払いが長期にわたって続くことになるため、その点を考慮して資産の管理や税務上の計画を適切に行う必要があります。
ChatGTP3.5
相続時精算課税制度の内容とまったく違います。これはChatGTPの使い方が悪いと考えられる。さすがに、1文の指示だけでは期待通りの文章は生成できない。
ウェブライターとしての注意点
ChatGTPの使用を禁止している案件に限らず、上記のような内容をそのまま納品してしまうとトラブルになる可能性があります。加えて、このような原稿の校正を引き受けないように注意したい。サンプルで拝見した原稿がまともで、残りの原稿がChatGTPで作成した原稿の場合、最初から執筆し直す必要があるため、安易に引き受けないようにしなければなりません。
校正・校閲の単価も執筆と同程度にするなどの対応をしましょう。
国税庁の情報を提供して「相続時精算課税制度」を書いてもらう
ChatGTPはどのように使用すれば、有効活用できるかを考えて、試行を繰り返して適切な使い道を探す。前章の、単に「相続時精算課税制度について教えて」という質問では、基本的に満足のいく回答は得られない。そこで、国税庁の情報をもとにわかりやすくまとめられるかを試してみました。
慣れている人であれば、国税庁の制度解説も理解できるが、基礎知識がないと理解するのに時間がかかる。ChatGTPを使ってわかりやすく解説してもらえると、何かと役に立つかもしれない。
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子孫などに贈与された財産に対して適用される贈与税の制度です。以下にその概要をまとめます。
概要
- 対象: 60歳以上の親や祖父母などから18歳以上の子孫などに贈与された財産に適用される。
- 申告期間: 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に申告書を提出する必要がある。
- 制度選択: この制度を選択すると、その贈与を受けた財産は暦年課税に変更される。選択後は変更不可。
適用対象者
- 贈与者: 60歳以上の親や祖父母など
- 受贈者: 18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫
適用対象財産等
- 制限: 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。
計算方法
- 贈与税額の計算:
- 贈与財産の合計額から特別控除額を差し引き、残額に20%の税率を適用する。
- 贈与財産が特定贈与者以外からの場合は、暦年課税の基礎控除額110万円を適用して計算する。
- 相続税額の計算:
- 贈与財産の価額と相続財産の価額を合算し、その金額から既に納めた贈与税相当額を差し引いて相続税額を計算する。
手続き
- 申告期間: 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで
- 申告先: 納税地の所轄税務署
以上が相続時精算課税制度の要点です。
ChatGTP3.5
前章よりもかなりわかりやすく、制度内容に近づいているが、間違いも見られます。ちなみに、相続時精算課税制度に110万円控除が適用できる改正前の内容である。この回答でも、相続時精算課税制度について理解している人が修正しなければならないし、違う表現を使った方がわかりやすい箇所もある。
またほかのサイト運営者も同様の質問で原稿を作成し、サイトに公開すれば、サイトの独自性は失われるため、SEO的な問題が発生する。
一致率は67%
試しに上記の原稿をコピペチェックツールで判定したところ、一致率は67%と高い割合だった。これでは公開できないし、商品として納品することもできない。
Copliotにも相続時精算課税制度について質問する
国税庁の「相続時精算課税制度」のページをもとに、Copilotにも質問した結果が次のとおりである。
相続時精算課税制度は、贈与税の一種で、相続時に税金を支払う制度です。以下に詳細を説明します。
- 対象税目: 相続税、贈与税
- 概要: 相続時精算課税の制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。また、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
- 適用対象者:
- 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など。
- 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。
- 適用対象財産等:
- 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
- 計算方法:
- 贈与税額の計算:
- 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年分以後、特定贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。その贈与税の額は、特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
- 相続税額の計算:
- 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、特定贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
この制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度であり、2024年1月以降の改正により、新たな非課税枠が導入されています。具体的な詳細や計算方法については、税務署や専門家に相談することをおすすめします。
Copilot
Copilotの回答は、正確である。相続時精算課税制度を知らない人に理解してもらうための、わかりやすい文章ではないが、GTP-4をベースにしているだけあり、より信頼できる。ただ、記事を商品として納品できる質には届いていない。
Copilotを利用する場合の課題
CopilotはchatGTP4.0を搭載しているためか、chatGTPよりも正確な情報を得られた。ウェブライターとしてどのようにとらえたらいいのか、課題をまとめる。
- 上手くまとまっているように見えるが、初心者にはわかりにくい。
- 2,500万円などの重要な数値が抜けている。
- 情報が正確かどうかの専門家による校閲が必要である。
しかし、ここまでの完成度であれば、仕様書を付けて条件をつければ期待通りの記事になる可能性は高い。
まとめ
文章生成AIを使用する際は、生成された文章をそのまま使用するのではなく、情報の正確性を確認し、専門家による校閲を行うことが重要である。
オリジナリティのある質の高いコンテンツを作成するためには、AIによって生成された文章を編集し、独自の見解や情報を追加する必要がある。AIの技術は日々進歩しているが、現状では思い通りの原稿を書くことは難しいだろう。
しかし、AIを上手に活用し、人間のcreativityと組み合わせることで、将来的により説得力のある記事を作成できる可能性がある。そのためにも、AIの適切な使用方法を理解し、試行錯誤を重ねることが求められる。