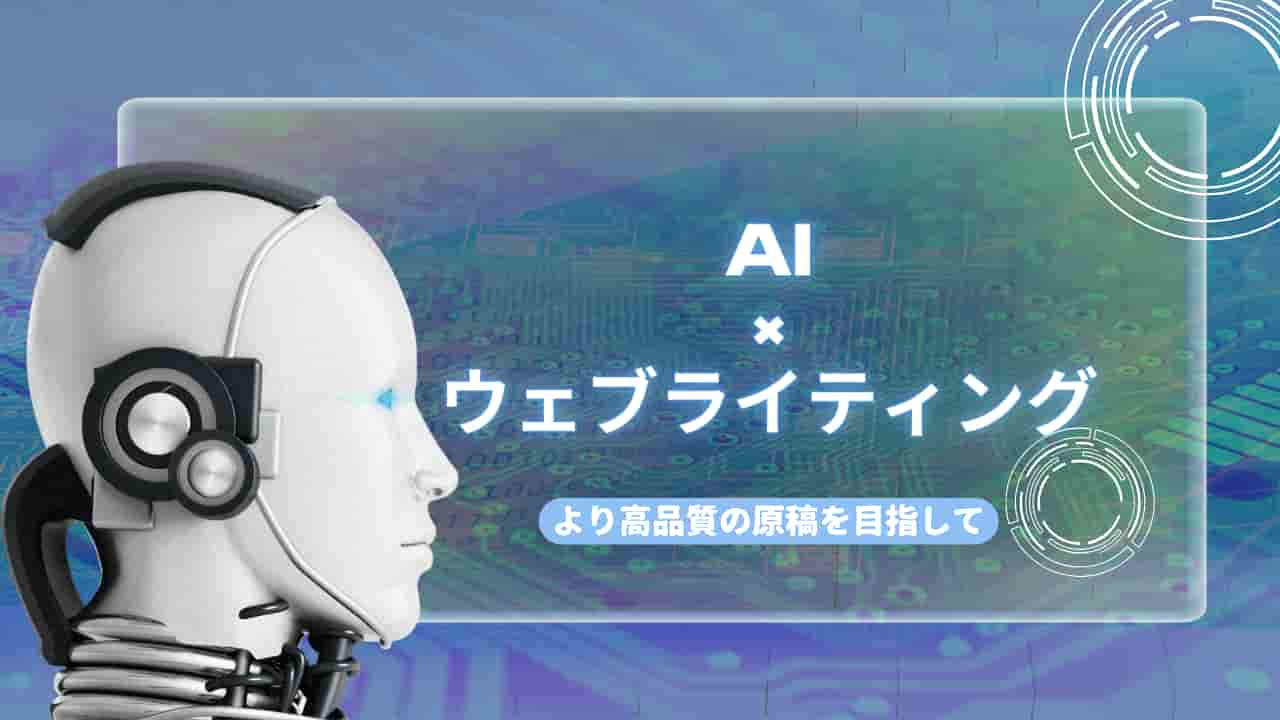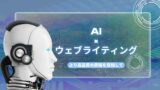AIとの対話では、Markdownを活用して条件を細かく伝えることが重要であり、指示書を細分化することで、より詳細な条件設定が可能になる。
また、制約条件を緩和し、AIの柔軟性を確保することも必要である。文章生成AIは便利なツールであるが、使いこなすためには試行錯誤が求められる。
ただし、有料版のAIを使用することで、これらの課題が解消される可能性もある。
ここまで、無料版の文章生成AIを使い、AIの性能と対話方法を考察してきた。どのように対話すれば、期待する回答を得られるかをまとめる。AIに詳しい人にとっては当たり前の内容だが、初めて触れる人にとっては有益な内容だろう。
文章生成AIとの対話で知っておくべきポイント
ここでは、文章生成AIとの対話経験を踏まえ、知っておくべきポイントをまとめる。これまでの工程を知りたい方は下記のリンク先の記事を読んでいただけるが、ここのポイントをおさえておくとよい。
markdownを活用する
制約条件を数多く伝える際には、上手にまとめて伝える必要がある。その際には、markdownを使うとよい。
Markdownは、テキストを装飾するための軽量マークアップ言語である。その名前は、マークアップを「ダウン」(軽減)することから名付けられた。HTMLに変換することが可能で、ウェブ上での文章作成に適している。
プレーンテキスト形式で人間が読み書きするのに適した構文で、有効なHTMLに変換できる。ウェブライターは複雑なHTMLタグを覚えることなく、ウェブコンテンツを作成できるようになった。
Markdownの特徴は、そのシンプルさと柔軟性である。基本的な構文は非常に簡単で、数分で学ぶことができる。また、多くのテキストエディタやコンテンツ管理システムはMarkdownをサポートしており、ユーザーは自分の好きなツールでMarkdownを使用することができる。
Markdownは次のような要素を使用できる。
- 見出し:
#、##、###などを使用する。 - リスト:
-や*を使用して箇条書きのリストを作成し、数字を使用して番号付きリストを作成。 - 太字:
**を使用してテキストを太字にする。 - 打ち消し線:
~~を使用してテキストに打ち消し線を引く。 - リンク:
表示テキストの形式でリンクを作成する。 - 画像の埋め込み:
!代替テキストの形式で画像を埋め込む。 - コードの埋め込み:“`を使用してコードブロックを作成する。
- エスケープ:
\を使用してMarkdownの記号をエスケープ(無効化)する。 - テーブル:
|と-を使用してテーブルを作成する。 - 引用:
>を使用してテキストを引用する。
見出しの#はよく使われているため、これから見る機会は多くなるだろう。
条件を細かくするために、指示書を細分化
文章生成AIに「〇〇をテーマに4000文字の記事を書いて」という指示だけでは期待通りの文章にはならない。さまざまな条件を設けて、誘導する必要がある。
- 条件が多いほど、期待通りの記事になる(△)
文章生成AIにもこのことを確認し、期待通りの記事になるか試行回数を重ねた。しかし、Copilotもclaude3(Sonnet)は、条件を見落とす。文字量が多すぎると、肝心な条件を見落とすため、何度もやり直ししなければならない。なお、3つ程度の条件でも見落とすことがあるが、よくわからない。ただ、文字量が多すぎると、整合性を保つためか、見落としが発生するのは事実のようだ。これは、あくまでも無料版でのお話。
そこで、条件を詳細に伝える必要性はあるため、指示書を5つに分割することにした。どのみち、やり直しは発生するので、工程ごとに人間のチェックを入れて次に進める流れとした。
- 条件を増やすために、指示書を分割する(〇)
この方法であれば、指示書ごとにさらに細かい指定ができる。将来的にはapiを使い自動化するので、手間は気にならなくなるのではないかと予想している。
「制約」を制限し、「容認」を最大限に活かす
指示書に、「〇〇をしないこと」という制約を設けることがある。一方で、「〇〇文字以内で」という要件(容認)も必要となる。AIの特徴上、制約が多いと、期待通りの結果を得られない可能性がある。
どうしても期待通りの結果を得られない場合は、制約条件を緩和したり、削除したりするか、「容認要件を優先すること」などの指示を与える必要がある。こうすることで、AIの柔軟性を確保できる。
まとめ
これまで、無料版AIと向き合ってきた内容、対応方法を解説した。有料版claudeは高性能であるため、これまでの課題は有料版にするだけで解消するかもしれない。いずれにしても、便利なAIだが、使いこなすためには、試行錯誤が必要である。